今回は、生薬の薬能についてです。
生薬は、いろいろな分類がありましたが、薬能とよばれる治療効果によっても分類されます。
治療効果によって
- 病気の原因となる邪気を身体から除くもの
- 邪気による症状を改善するもの
- 気血水に関連した病態を改善するもの
- それ以外の治療効果をもつもの
の、4つに分けられます。

病気の原因となる邪気を身体から除くもの
代表的なものとして
- 解表薬
- 瀉下薬
があります。
解表薬
身体の表面にある邪気を体外に出すものです。
- 悪寒が激しく口が乾かない場合に用いる・・・辛温解表薬(麻黄、桂枝、細辛など)
- 明らかな発熱があり、口が乾いている場合に用いる・・・辛涼解表薬(薄荷、葛根、牛蒡子など)
にわけられます。
瀉下薬
排便を促進し、体内の余分な熱を除くものです。
- 作用が強い・・・攻下薬(大黄、芒硝など)
- 便を軟らかくする・・・潤下薬(麻子仁、桃仁、杏仁など)
邪気による症状を改善するもの
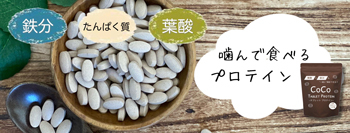
代表的なものとして
- 清熱薬
- 散寒薬
があります。
これらは、邪気が身体の内部にあって解表薬では取り除くことができない場合に用います。
清熱薬
熱感を伴う症状に有効です。
石膏、知母(ちも)、大黄など
散寒薬
冷感や寒気を伴う症状に有効です。
附子、桂皮、乾姜など
気血水に関連した病態を改善するもの

代表的なものに
- 補気薬
- 理気薬
- 補血薬
- 駆瘀血薬
- 化湿薬・利水薬
- 補陰薬
があります。
補気薬
気の不足を補い、身体全体の機能を高めるものです。
人参、黄耆、山薬など
理気薬
気の流れのうっ滞を改善するものです。
陳皮、厚朴、香附子など
補血薬
血の不足を補うもので、全身の栄養状態や神経系の機能を改善します。
当帰、地黄、阿膠(あきょう)など
駆瘀血薬
瘀血という血が停滞した状態を改善するものです。
牡丹皮、桃仁、川芎など
化湿薬・利水薬
化湿薬は主に消化管内の水分を除きます。(厚朴、半夏、朮など)
利水薬は体内の水分を利尿により除きます。(茯苓、猪苓、沢瀉など)
補陰薬
人体を構成する血液や水分などが不足した状態を改善するものです。
麦門冬、天門冬、地黄など

それ以外の治療効果をもつもの
ここまでまとめた3つ以外にも重要な治療効果が存在します。
代表的なものとして、
- 去風湿薬(きょふうしつやく)
- 止咳化痰薬(しがいけたんやく)
- 安神薬
- 鎮痙薬
- 固渋薬
があります。
去風湿薬(きょふうしつやく)
体外の湿気により関節痛や筋肉痛が起こるのを改善するものです。
威霊仙、独活など
止咳化痰薬(しがいけたんやく)
咳や痰、喘息などの呼吸器系の症状を改善するものです。
杏仁、五味氏など
安神薬
精神不安や不眠などの神経系の症状を改善するものです。
竜骨、牡蛎など
鎮痙薬
てんかん、ふるえ、興奮などの症状を改善するものです。
天麻、釣藤鈎など
固渋薬(こじゅうやく)
体内のもの、たとえば便や尿や精液などが漏れるのを自分でコントロールできない症状を改善するものです。
山茱萸や五味子など
生薬のもっている治療効果が多岐にわたっていて、一つの項目に絞ることが困難です。
例えば、五味子は止咳化痰薬と固渋薬の両方の薬効を持っています。
厳密に分類することはできないということを理解しておく必要があるようです。
次は、生薬の組み合わせについて勉強したいと思います。
(@^^)/~~~

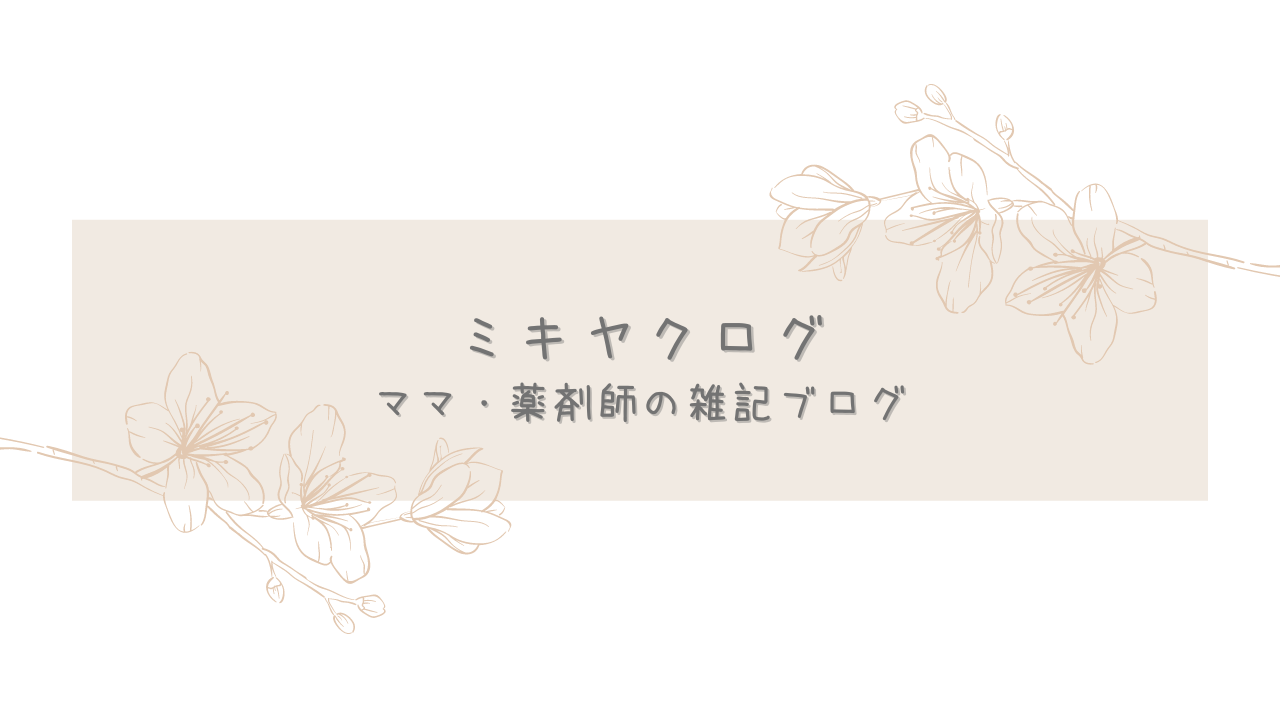


コメント