
薬学部で勉強する科目のうち「薬物動態学」という科目があります。
正直とても苦手でした(;^_^A
今も苦手です。
でも、薬剤師として、これを理解していないと真に薬を理解できていないような気がするので、
今更ながら勉強していきたいと思います。

薬物動態学(PK)とは
体の中に入った薬物が吸収され、組織に分布し小腸や肝臓で酵素により代謝され、排泄されるまでの一連の流れ絵を解析することで薬物と体の相互作用を研究する学問のことです。
この、体内での薬物の一連の流れを
- 吸収(absorption)
- 分布(distribution)
- 代謝(metabolism)
- 排泄(excretion)
それぞれの英語の頭文字をとって
ADME(アドメ)と呼びます。
つまり、薬物動態学はADMEに関する研究を行う分野ということです。
では、薬局の薬剤師にとってこの薬物動態学がどう必要なのか?

薬局薬剤師にとっての薬物動態学

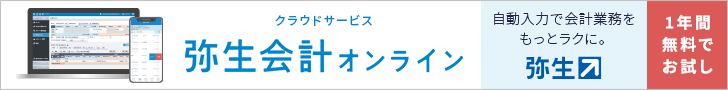
薬局で薬剤師がかかわるうえでは、
患者さんが薬を服用した際の
「効果発現までの時間」や
「ほかに服用している薬や摂取している飲食物との相互作用」
「血液検査などの結果で見られる生理機能の状態と薬の効果や副作用」
などの把握や予測を行うのに重要となります。
薬局で服薬指導の時に、患者さんから
「飲んでからどのくらいで効きますか?」
「次に飲むまでどれくらいの時間を空ければいいですか?」
などど聞かれることがよくあるかと思います。
これらの質問に正確な回答は個人差があるため難しいのですが、
添付文書やインタビューフォームの薬物動態の情報を読み解けば、
おおよその予測を伝えることは可能です。
薬物動態学の用途
薬物療法に関して
- 吸収の評価
- 連続投与計画の設定
- 疾病等の投与量の設定
- 投与経路の選択及び決定
- 薬物の体内蓄積性の予測
臨床および診断に関して
- 血中薬物濃度および薬物の尿中排泄データの一般化
- 病態および遺伝的疾患の評価
病理学に関して
- 薬物の吸収・血中濃度・分布・排泄と薬効の発現・強度・持続時間の関係の解析
- 種差・性差等の解析
毒性学に関して
- 毒物の体内蓄積の解析
- 毒物の吸収及び代謝の解析
- 毒性の個体差・種差・遺伝的要因の解析
- 環境薬物動態学

薬力学(PD)
薬力学は、作用部位における薬物量・濃度と薬効の関係について研究する学問です。
薬物動態学のパラメータと合わせてPK/PDと総称されます。
最後に
今回は薬物動態学とはなんぞや?についてできる限り数式とかを用いずに説明でるような内容になっているかと思います。勉強したことそのまま記載しているので、誤字脱字などあればすみません。
また、記載することでより一層理解できるようになりました。
これを機会にもっと詳しく薬物動態学について学んでいこうと思います。
では(@^^)/~~~

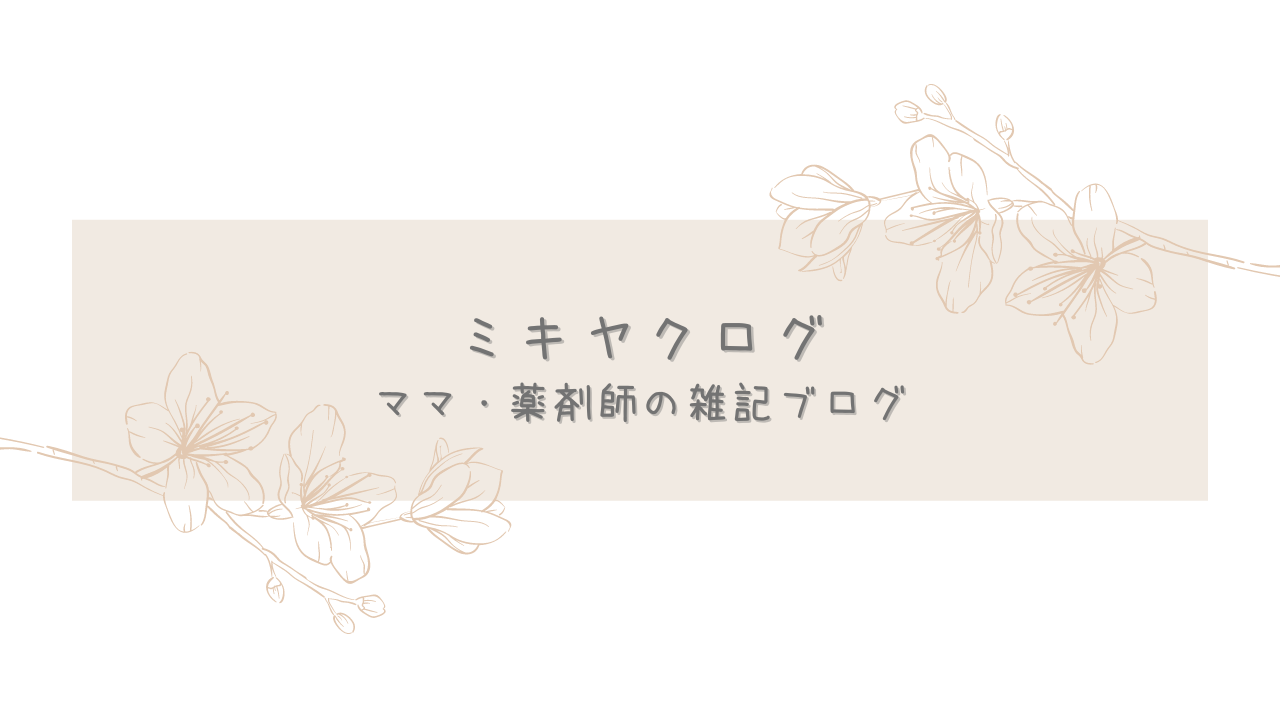



コメント